総括

今回も第三土曜日が取れなかったため、二土会になりました。場所も、万世橋区民会館です。

| 粕谷 さん | |

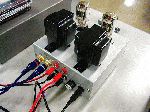

|
高電圧スィチング電源使用10EM7シングルアンプ
試作品のスイッチング電源を使用したアンプ。DC15~24Vを220V程度に昇圧していて、電流は75mA程度採れ、効率は70%程度とのこと。電圧は 変更できるとのことですが、高くすると電流がとれなくなります。気になるノイズレベルは45mV程度で、問題のないレベルとのことでした。 スイッチング電源の影響なのか、華やかで綺麗な音でした。 |
|
出品者のコメント: 電源トランスを使用せず、ACアダプターと高圧スイッチング電源を用いるとこんなにコンパクトな真空管アンプになります。今回はなるべくベーシックな回路 でデモを行いました。スイッチング電源はDC200V~300Vをボリュームで変えることが可能です。スイッチング電源のノイズは45mVでしたが、30 分ほど経過すると22mVまで低下しました。さらにLCフィルタを使って0.25mVまで低減できています。 高圧スイッチング電源はW62mm×D43mm×H40mmとコンパクトです。価格はここでは書けませんが、電源トランスよりはかなり安いはずです。発売は2013年1月~2月を予定しているそうです。 |
|
| 大橋 さん | |


|
THS6012使用MITアンプ
発振を抑えるのに苦労したとのことです。この状態からちょっと変えるだけで、発振するするそうです。バイアス回路無しA816/C1626のSEPPなの で、5kHzよりも周波数が高くなるとスイッチング歪が盛大に出るとのことですが、歪みっぽい音にならないのでよしとしているとのことでした。 THS6012を使用しているためなのか、力強い音でした。 |
|
出品者のコメント: ICの発熱を抑えるため電源電圧を低めにしたのと、手持ちのシリーズレギュレータが400mAと非力のため、出力は2W@8Ωと非力ですが無事鳴らすこと ができて、ほっとしました。THS6012もブリッジ化などまだまだやることがありそうですが、変換基板に半田付けするのが大変だったのでMITはちょっ と一休みします。 |
|
| 見元 さん | |


|
Luxアンプ(LT1364)+ノイズフィルター(見元)
stereo誌付録アンプの電源はノイズが少ないとのことでした。オペアンプは、LT1364に変更しているそうです。 ノイズフィルターを使うと、特定の音域で少々詰まってささくれる感じはありますが、全体では伸びのある音という不思議なバランスでした。ノイズフィルターを外すと、若干きつくはなるものの、詰まる感じが緩和されました。 |
|
出品者のコメント: 三土会終了後、レギュレーターやノイズフィルターは枝葉ではないかと考えるようになりました。真空管アンプの良さ、メーカー製アンプの安定感、とまだまだアンプの根本でやらなければならないことがあると感じた次第です。 |
|
| 安江 さん | |



|
コカコーラ缶アンプ製作途中報告
製作途中のアンプを説明して頂きました。強度の高い缶を探すのに苦労しましたが、280mL缶だと使えるのでこれで製作しているそうです。プルタップ付きの面はボリュームつまみとして利用するので、飲まずに利用しているとのこと。 |
|
出品者のコメント: おなじみTDA1552Qを用いたアンプです。 回路はネット上で紹介されている回路です。 アルミ缶の加工の話だけで、持ち時間をこなす…! これってアンプの会…? |
|
| 石田 さん | |


|
DSD変換DAC
表現力に優れるDSDですが、あまり聞く機会がないです。そこで、PCMをDSDに変換する基板を利用したDAC を作ったとのことでした。入力は三種類に対応しています。将来はDACも二種類搭載する予定だそうです。 DSDは奥行き感があり細かい音まで再生できる自然な音でした。これをPCMにすると、平面的な音になりました。 |
|
出品者のコメント: ようやく三土会に間に合って音出しができたDACです。まだやり残した部分がありますが、基本のDSD変換とPCMの比較試聴ができて良かったです。 個人的にはDSDの方が広がりと奥行き表現や細かいと音の分解能が高くなり、低域の躍動感などが高まった予想通りの音で、まあまあ作った甲斐があったと思います。 今後はもう一つのデジタルフィルターによるDSDDAC部分とか細かい付加部分のテストとデジタルチャンデバ改造、もう一台のDSD変換DACの製作でマルチアンプのデジタル部分の全面更新をしたいと思います。 |
|
| 前田 さん | |


|
太鼓の録音
太鼓の音の音圧レベルが高くて、マイクの近くにいる人の話声がほとんど聞こえないという難しい録音です。通常の録音レベルがだと問題なく録音できていたマ イクアンプが、太鼓の音だとレベルが高すぎて出力が非対称になってしまうことが分ったとのことでした。マイクアンプの問題点をチェックするためにも、一 度、挑戦してみるのかいいかもしれません。 今回はバックアップ用に後ろで録音していたファイルを再生して頂きました。 |
|
出品者のコメント: バリバリのクラシックファンの抜作三太郎こと前田@厚木です。 マイク作成後、ちゃんと特性を測っていなかったら、とんでもないものができていたのに気づかずに使い続け、太鼓や鐘などの衝撃音を録音して初めて気がついた、というまぁ情けない話でした。 修正してまた挑戦してみます。 |
|
| 蝦名 さん | |




|
セラミックハンダごて用温度コントローラ
Toshi工房那須さんの設計した「半田ごて用温度コントローラ」を若干変更して製作したものです。こて先の温度が上がり過ぎないために、ハンダ付けが楽になります。整流した130Vくらいの直流を使用しているので、アースパターン周りなど、パワーが必要な場合のハンダ付けも簡単になります。 岩井さんが持参してくれたこて先温度計を使って通常使用している温度を測定してみましたが、300℃くらいでした。ハンダが乗りやすい小さな部品だと、このくらいでも使えることが分りました。 |
|
出品者のコメント: このハンダごて温度コントローラは、二作目です。CXR-30に付属するヒータは室温での抵抗が220Ωもあって、細かいハンダ付けしかできない仕様なの で、ヒーターをPX-60Hに変更しています。こちらだと、室温で約35Ω、こて先が350℃のとき約100Ωで、逆に温度コントローラが無いと温度が高 すぎて使うのに苦労すると思います。 温度コントローラを使ってみると、プリント基板のハンダ付けは320℃くらいで問題なく作業できます。アースパターンのような大きな面とか、大きな部品のハンダ付けだと、360~370℃くらいがいいようです。 |
|

